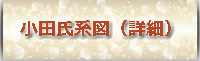源姓山縣氏流小田氏とは
清和天皇九代の苗裔、従三位兵庫頭源頼政の二男国政の後裔と謂われる。治承4年(1180)、以仁王の令旨を奉じて平家追討の烽火を挙げた頼政が宇治平等院で敗死したとき、一族ほとんどが道連れになる中で、美濃国山縣郡にいて死を免れたのが国政である。しかし、源氏の再蜂起を恐れた平家によって、安芸国豊田郡小田(現・広島県東広島市河内町小田)に配流となった。この地では先住地に因み山縣氏を名乗り、9代・約280年間過ごす。現在も小宇治屋長者墓所跡に宝篋印塔・五輪塔が残る。
やがて山口の大内氏が台頭してきて、西条(現・東広島市)の鏡山城を拠点に付近を攻略し始めたため、安芸太守・武田氏を頼って、安芸国山県郡穴村堤(現・広島県安芸太田町都津見)に移住する。長禄元年(1457)のことで、頼政の家臣猪早太の後裔を伴っている。これ以降先例に倣って小田氏を名乗るようになる。やがて武田氏に代わって毛利氏が台頭してくると、毛利・吉川について厳島合戦、備中高松城攻防戦、文禄・慶長の役をはじめ数々の戦に出陣している。戦功によりやがて山県郡代官職につくが、慶長5年(1600)雲州月山富田城下で配下の侍が不祥事を起し、責任を取って止む無く代官を辞職する。またこの年秋、毛利・吉川の一員として参戦した関ヶ原の戦いで敗れ、武士を止める決断をする。家伝では“中世流浪し”とあるが、これ以降広島県西部一円に広く分散することになり、“郷士の家風一変して”多くが農民となる。
堤(現・都津見)をはじめ付近一帯には、宝篋印塔・五輪塔十数基、石塔類(浄土真宗)、菩提寺、祖霊社等々、数多くの史蹟が点在する。また、地名、屋号には先住地河内町小田と共通するものが数多くある。