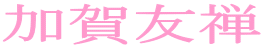
|
苦闘の中から独自の童の世界を賀友禅に
初代・由水十久
|
|
大正二年、石川県金沢の西北の港町大野の料理屋に生まれました。
絵の好きな少年で十歳のころから玉井紅隣師のもとで墨絵の勉強をし、
また中村直春師について加賀友禅の技術を習得しました。
絵描きになりたかった由水さんですが、両親に反対され友禅で身を立てることになります。京都の友禅作家紺谷静蕉師のもとで本格的な友禅の修行をしました。
二十年間、京都で友禅の仕事をしますが、戦争が激化してくるときものの注文がなくなり、機械の図面書きなどして生活を支えました。
戦争が終わると金沢に戻りますが、日本全体が戦後の大混乱の時代で、
彩筆で生きる以外に手段のない由水さんは、すさまじい生活苦との闘いだったそうです。転機の一つになった「東海道五十三次」や「源氏物語」を題材に選んだこと、由水さんの友禅の童には愛らしく品があったことです。
由水さんの描かれた童はただ可愛いだけではなく、どの模様にも物語があり心打たれものがあります。
歌舞伎・舞踊・能などがお好きでしたが、何よりも好きだったのは文学でした。自分の好きな文学のイメージを徹底的に追及した独自の友禅の世界です。
|
|
二代由水十久さんは、初代の作品の作風を完全に引き継いだのではなく、
多くの制約を乗り越えながら、新しい画題や技法も発表しながら「自分の童子」を生み出されています。作品の構想は、知識や興味の範囲の広さから、その深さは驚くほどで日本の古典文学、古典芸能、年中行事や季節の草花の言葉などが画題になっています。また外国の音楽の世界やサッカーのワールドカップも画題にとりいれられ童子の「見立」というわが国独特の面白さを表現されています。その童子が着る衣には、人物を表す文様が繊細な図案となり、その時代考証の正確さには驚かされます。先代が切り開いてきた童子の世界、二代目によってより世界を広げ、より繊細で際立ったものへと変わってきました。
|
夏・・・
源氏物語の野分に「御直衣(源氏のお召料)、花分綾を(花散里が)
このころ摘み出たしたる花(露草)して、
はかなく(薄く)染め出でたまえる。
いとあらまほしき色(申し分のない色)したり。
(源氏は)“中将(夕霧)にこそ、かようにては着せたまはめ、
若き人のにてめやすかめり”などやうのことを
(花散里に)聞こえたまひて、わたりたまひぬ」とあり、
摺染ではなく花で直衣を染たとされています。
いつの頃からかわからないですが青花紙を作るためにつくり出された
ツユクサの変種、花が大きくその花の汁を取って青花紙がつくられます。
青花紙をちぎり水に浸し、その汁で、
友禅染や絞り染の下絵を描くのにも用いられます。
描いた下絵は水につれると流れ落ちてしまいます。
ツユクサはどこにでもある普通の一年草で、
6〜9月頃次々と青紫の花をつけます。
そんなツユクサの花を絽の生地に描かれた加賀友禅の夏の訪問着です。
夏の暑さにも負けず小さな花を次々に咲かせる露草、
直向なつよさと青紫が清涼感を感じさせてくれます。
さくら・・・花吹雪
桜、さくら。冬が寒かった年は、いっそうこの花への想いが募ります。
花冷えという言葉もあるように、四月になっても寒い日があります。
さくらの花が咲いてくれれば、春が来る。
加賀の武家では野外での宴に加賀友禅を衣桁に掛け飾りそれを愛で
ながら酒を酌み交わしたりしました。
美を彩る多彩な色づかい草花の咲き乱れる様は
加賀百万石前田家のもとでつちかわれた貴賓・気品を
ひっそりかもしだしてくれます。
また、茶の湯では炉と風炉の季節となり、
また火の季節と風の季節です。
その火と風の結び目に咲くのが桜の花です。
だから桜の花色は淡く、薄ぼんやりしていると・・・。
加賀友禅 寒晒
金沢の加賀友禅は、浅野川の水の恵みをうけて女性の心を魅了する、
あの美しい友禅をうみ出してきました。
友禅は、まず糊で模様を描き、そこに色を差すとその上に厚くのり伏せ、
地染めをします。
最後に水洗いをして、のりを洗い流して仕上げます。
水洗いは友禅流しと呼ばれ、浅野川でもかつてはよく見られる光景でした。
川の水で、とりわり寒の冷たい水で晒したほうが、発色がいいといわれて
います。
初花・・
春に最初に咲く花
梅は花の“魁”ともいい春いちばん早く美しい花と香りを贈ってくれます
春浅い折、訪ねてくる方には梅の一枝なりとも用意したいものです。
一輪挿しに生けても絵になります。
紅梅の花時は、白梅より少しおくれますが、
その分、春の艶を届けてくます。
冬・・・
金沢の四季物語なかで必ず思いうかぶのが、
冬景色の雪吊りではないでしょうか。
特別名勝、兼六園。日本三名園の一つとして知られるこの庭園は、
六つのすぐれた景観、「六勝」を兼ね備えていることから、その
名前がつけられました。
林泉廻遊式庭園という様式のなかに、数々の意匠を散りばめて、
春夏秋冬(四季)の景観を豊かに描き出しています。
加賀友禅の着物のなかにもこの景観を図案にとり入れた作家が
たくさんいらっしゃいます。
加賀友禅作家の奥野義一さんの黒留袖もその一つです。
巡るめく四季の金沢兼六園を、すそいっぱいに巡らし、
春・夏・秋・冬の人生をつつんでくれます。
加賀友禅作家 奥野義一さんの黒留袖、「兼六園の四季」です。
秋・・・
実る秋
稲と麦、よく比較されますが、麦は実っても頭を垂れてません。
稲は籾の重さで、頭が下がります。
加賀友禅作家 矢田博さんの黒留袖、「稲穂」です。
幾久しく、豊かに稔ることを願う心と何時までも頭はひくく、
控えめな心をこめた柄で望む祝いの席。
色合いの広さが、秋以外の季節に実りを待ちどうしくさてくれそうです。
加賀友禅作家 矢田博さんの黒留袖、「稲穂」です。
加賀友禅ものがたり
金沢に古くから伝わるお国染めが、加賀友禅にどう結びつくか
歴史上大きな役割をはたす重要な人物が宮崎友禅斎です。
江戸中期、友禅斎は京都の知恩院の門前で、扇に絵を描いて売っていました。
都ではその雅びと風流が時の流行になり、都の女性たちが競って買い求めた。
宮崎友禅斎という名前は瞬く間に都じゅうに知れ渡ることに・・。
宮崎友禅斎という人物は、有名なわりには、多くの不明な点が
生まれや没したところは、いろいろな説があり、京都・金沢とまちまちです。
おもに都で活躍していたのは確かで、井原西鶴『好色一代男』に
「扇も十二本、祐善(友禅斎)が浮世絵」と登場しています、
天和二年の頃の友禅斎の活躍が書かれてます。
晩年になり金沢に来ます、ここで一つ疑問が・・。
都で売れっ子なのにどうして金沢に行かなければならなかったのか?
そんな疑問がでてきます。
大正九年、金沢市の龍国寺というお寺で、友禅斎のお墓が発見されます。
これによって話が進展することに、金沢で亡くなったからには、晩年を
金沢で過ごしたことに・・。
金沢で生まれたとすれば、故郷に帰ったことに・・。
京都・金沢と、どちらも身びいきがあり、いずれにしても
謎多き人物には違いありません。
五百年あまり前、加賀の梅染と呼ばれる無地染めがありました。
梅の皮や渋で布地を染め、黄味がかった赤色になり、回数を重ね
手染めると赤くなりますこれを赤梅染と、さらに何度も繰り返すと
黒色染まりますこれを黒梅染といいます。
こうした無地染に加えて、模様染の技術も発達し、加賀兼房(兼房染)や
加賀紋(色絵紋)などのお国染(加賀染)がありました。
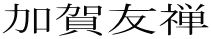
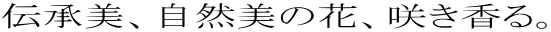
金沢は、風光明媚の町。季節が変わるたび、移ろいでゆくすばらしい
自然美で私たちの心を魅了してくれます。
かつて加賀百万石の城下町として栄えた武家社会の名残り、泉鏡花や
室生犀星を生み出した文学の町。
様々の文化がひとつになって完成されていった特有の美意識には、
はなりしれない深さが満ちています。
そして、長い歴史のなかでひとつひとつ形づくられてきた伝統工芸の
数々、加賀の自然と人々の感性から生まれた、心の美技ともいえます。
加賀友禅もそのひとつです。
古くから染色が盛んであった金沢には、加賀染、梅染、御国染などが
ありましたが、これらをもとにして宮崎友禅斎が完成させたといわれる
加賀友禅。花鳥山水をモチーフにした写実的で細微な模様、加賀五彩
と称される藍、臙脂、黄土、草、古代紫を中心にした多彩で優雅な
色使いを特徴とし、情感あふれる美の世界をしっとり染め上げます。
模様の外側から内側にかけてのぼかし、虫喰いと呼ばれる技法も
加賀友禅ならではの美しさをひときわ強めています。
金沢の風光明媚をそのまま映しとったかのような染めの精華、
加賀友禅は色あせることのない伝承の美の花です。

|