赤間石の古硯


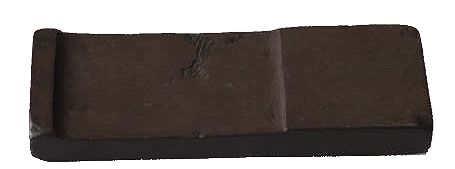
硯の裏が内側に削られていて、猿の足の形に似ているという
堤の小田家(中河内)に代々伝わってきた小さな硯(幅6.0cm×長さ17.0cm)があります。赤間石(山口県下関市)の硯です。一見して分かるように、墨を磨るところが大きくえぐれています。また周りの装飾は磨耗して、ほとんど判別できません。極めて硬い石がこれほど削られるには余程長い年月が必要です。 小田氏は徳川期には百姓に身を落としていますが、中河内の人たちは代々読み書きができたそうですから、その時代もこの硯を使い続けてきたはずです。したがってこのような変形も納得できます。
専門家によると、硯制は中国の鳳池硯から変形した日本特有の猿膝硯(さるあしけん・・・硯の裏側が猿の足のように湾曲・・・・ 平安末期の古硯の特徴で、軽くするための工夫か?)かもしれないということです。また、平安・鎌倉の頃、武将が陣中に携行したり、歌人が歌会に持参したりした小ぶりのものがあり、箙(えびら)の硯と呼ばれたそうですが、大きさからすればその可能性も十分あると考えられます。
古来、硯は中国から盛んに輸入されていますが、日本産の硯(和硯)は平安後期に発見された赤間石で作られたものが最古のようです。そして数が少ないため、破損せずに現存することは極めて稀で、専門家でも実際に見ることはあまりないそうです。
※ 裏面の中央に彫られた箇所があります。頼政の花押の可能性があるのではと想像しています。この時代になると、二合体(実名2字の部分(偏や旁など)を組み合わせて図案化したもの)や一字体(実名1字で同様に図案化したもの)など、花押の前身になるものが定着していたそうなので、これがそれにあたるのではと考えていますが、現在のところ証明できていません。

赤間硯とは
主要産地は山口県下関市・厚狭郡楠町です。赤間石は材質が硬く、緻密で、石眼や美しい文様があり、しかも粘りがあるため細工がしやすく、硯石として優れた条件を持っています。鎌倉時代の初めに、頼朝によって鶴岡八幡宮に赤間硯が奉納されたという記録があります。徳川期には、原料となる石が採れる山は御止山(おとめやま)として基本的には入山を禁じられ、参勤交代の贈り物等として硯が必要になると、藩主の命令で採掘がされました。こうした事情から、長州藩の名産として一般には簡単に手に入れることのできないものでした。
(日本の伝統的工芸品館ホームページより)
想像できること(頼政遺愛硯?)
この硯がもし本当に平安末期の猿膝硯なら、どんなことが想像できるでしょう。 配流されてきた広島の片田舎でそんな逸品が手に入るはずはありませんから、考えられるのは頼政の使っていた品ではないかということです。 宇治の平等院で敗死した頼政は、一方の司令官だから、戦の指示書を書くために硯を携行していたはずです。辞世の句を認めるときにも使ったはずです。歌人でもあった頼政は硯を大切にしていたでしょうから、死に臨んでそれが失われるのを惜しみ、家来に託して国政に届けるよう指示したのではないでしょうか。それが八百有余年の時を越えて現在まで伝わってきている。そんな想像が拡がってきます。
