小田(松堂)義鏡
小田義鏡(号・松堂)は正覚寺が浄土真宗に改宗後の初代住職・空鏡の三男として生まれる。二代目住職になったが、学林修行を志して住職を弟の義証に譲り上京した。勉学に励み、次第に本願寺派二代目能化知空に認められるようになった。やがて湛如の教育係を仰せつかる。湛如は14代宗主寂如の十男として生まれた。幼少より病弱だったが、兄弟がつぎつぎと早逝するなかで、次第に跡取りの期待が高まるようになる。ところが当時の西本願寺は一種のお家騒動のような状態にあった。15代宗主として九条兼晴の子を初めて養子に迎えいれたのである。将軍家の意向もあったといわれているが、代々宗主の子供の中から後継ぎが選ばれてきたそれまでの伝統を崩すことから、宗門の中には根強い反対があった。そのような事情もあり、義鏡は湛如に西本願寺の未来を託そうと必死で務めた。その甲斐もあってか湛如は24歳で宗主の座に就く。ところがそのわずか3年後、湛如は急逝してしまう。自殺だったともいわれるが、義鏡の落胆はいかばかりだったか。失意のうちに本山を辞して正覚寺に戻る。この頃はすでに晩年の境涯にあり、正覚寺本堂で宗学の講義を行いながら悠々自適の生活を送る。宗学の講義を聴きに安芸門徒は言うに及ばず、遠くは京阪神・九州などから多くの僧侶が集まったという。弟子からは安芸門徒を代表する僧侶がたくさん出ている。
義鏡の掛け軸
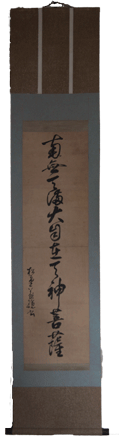
義鏡の名号で、”南無天満大自在天神菩薩”と書かれている。浄土真宗では通常「南無阿弥陀仏」という名号を掲げるので、これは義鏡の宗学上の新境地を表しているといえる。「天満大自在天神」というのは菅原道真の御霊に追贈された神号だが、義鏡が菅原道真に帰依していたとは考えにくい。「天神菩薩」=「天親菩薩」というのは世親を指し、興福寺北円堂に安置されている世親像が名高い。世親は唯識思想を学び、体系化することに努めた人物で、浄土真宗の宗祖親鸞が選定した7人の高僧の一人である。義鏡がその中でも特に世親の生き方に共感し、帰依していたと考えた方が納得できる。義鏡の書いたものは本人の遺言ですべて焼却されたので、今となっては確かめることはできないが。さらに想像を逞しくすると、当時の仏教界が堕落していると感じ、親鸞の時代の初心に帰るべきだと考えていたのかもしれない。そしてその夢を若い宗主湛如に託していた。そんなことまで考えさせる掛け軸ではある。
