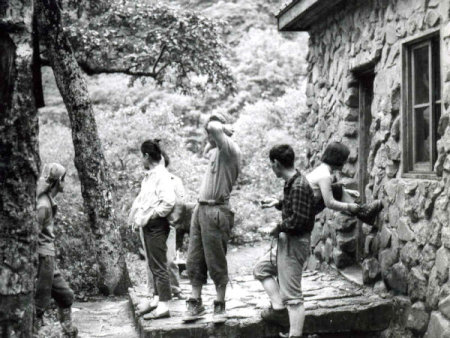|
�@�P�X�V�O�N�ȑO�̘b�ł���B
�����R���n�߂����A��R�́u���J�R�̉Ɓv�V��̊ԂɒN�̕�������Ȃ��Q�܂��������B�i�����R���Ԃ́u���J�����v�ƌ����Ă���
�@�����ɂ́A�Q�܂����ł͂Ȃ��s�b�P����犘���̑����i��������
�@�Q�܂́A�N�̂��̂�����Ȃ����A�������I�̏�ɂ���N���G�����`�Ղ��Ȃ�
�@�s�b�P���́A���ܒN���������o���Ă͎g�p���āA�܂������ɋA���ė���
�@�������X��ẮA�k�ǂ̓o���Ⓒ��܂Ŏ����Ă��������Ƃ�����
�@�s�b�P���͏��U��ŃV���t�g���Z����o���X�ǂł͗L���ł���A�d�Ă����̂ŁA�F�X�Ȑl���g�p���Ă����悤�ł������B
�@�g�p�����l�����́A�y���Ďg���₷�����A�X�̎Ζʂł͑���Ȃǂ��ȒP�ɐ��ƕ������A�����ł���Ƙb�������Ă����B
�@�������ĉ��N���������t�̂�����A�Â��R�̒��Ԃ����J�����ɏW�܂�u�R���y���މ�v���J�����B
�@�W�܂����̂́A�R�A�̎傾������̐l�������W�܂�A����x�̉�A�����R�x��A�Ďq�R�ʼn�A�o�_�R�̉�Ȃ�30�l�قǏW�܂����B
�@���̉�ɉ��͋����B���X�A�p�c�A���{�Ȃlj���������Ԃꂾ�B
�@���̒��ɁA���싞�q�������B����͍��Z�̐搶�����Ă����������ސE���A�v���Ԃ�ɓo���Ă����B
�@���ԒB�̒��ł͌ÎQ�ŁA�F�X�ȓo�R�҂Ƃ̕t������������ڒu�����l�ł������B
�@�Â����ԒB�ł���A���������x���܂Řb������オ��A���Ȃ���u��R��b�v�ł������B
�@�N���ǂ̕ǂ�o�����B�N���]�����B
�@�b��̏́B�������͒N���o�������̏��������s���Ă����B
�@����x���Ȃ���̗͂��肽�̂��A�ÎR�R�x��̏��̎q���ˑR��o�����B
�u���̏����ɐQ�܂����邪�ǂȂ��̂ł����B�H�삪�o��͖̂{���Ȃ�ł����v
�@���J�̏����ɂ́A�Q�܂̈ʒu���ς��Ə����ɗH�삪�o��Ƃ����A�\������A�N���G��Ȃ��Ȃ�A�z�R���������Y����Ă����Q�܂��������B
�@�����āA�N���炩�ƂȂ����J�����ɓ~�ɂȂ�Ƌ���u����j�v�̂��Ƃ�b�����B
�@�b���Ă������삪�b���n�߂��B
�@���N�O�A���J�����ɏ�A�̈�l�̒j�������B
�@�u�����v�Ƃ������́A���͋��Ȃ��Ƃ��������B
�@�~�ɂȂ�Ɠo���Ă��ẮA�t�ɂȂ�Ɖ��R���čs�����A�ǂ��ɋA�邩�����̐l�͒m��Ȃ��B
�@���͉��x�����J�����ŏo��������Ƃ����������A�ނ͉�������l�œV��̊Ԃ̕Ћ��ɋ����B
�@�ǖقŁA�����ė]���Ȃ��Ƃ͗����Ȃ��B�ǂ��ɏZ��ł���̂��A�N��́A�d���͂Ȃǂ������Ęb���Ȃ��B
�@�ނ͓~�̑�R��فX�ƎR��o��A�܂��A���J�����ɋA���ė��Ă͐Q�Ă͓o���Ă����B
�@�����đ��̎R�ɍs�����Ƃ��Ȃ������B�N������R�̑S�Ă��n�m���Ă����B
�@�ǖق��������A���߂���ƐF�X�ȕǂ̏�����A������ݓ��̊댯�ӏ����J�ɋ����Ă����B
�@�ނ̗F�l�B�́A���R���鎞�ɂ͐H���A�R���A�X�C�����������߂ɏ������Ă����B
�@���R����Ƃ��ɂ͗]�����H����R�������A�[��ɏ������˗����u���Ă������B
�@����ƍ��X�ⓡ�̘b�́A���̓��e������
�@�ނ̖��́u�[�얞�v�B
�@�[��́A�t�ɂȂ�Ƒ�R�̘[�ɂ��鍁��W���̐��{�q��Ŗq�v�Ƃ��ē����A�P�P���̐V�Ⴊ����ƌ��J�����ɓo���Ă���B
�@�����y�����̂��A��������l�œ��Ă����J�����ŁA�~�G�]�ƈ��̂悤�ɉ���������B
�@�~�̏����̒��͉������뉺�T�x�ȉ��ł���A�����ɂ͗뉺�Q�O�x�ȉ��̓����������B
�@��������l�ŏ����ɋN�����A�o���Ă���o�R�҂��ǂ�o�肽�����A���Ԃ����Ȃ��ƌ����ƃU�C�������B
�@�[��̌Â��F�l���́A�[��ƃU�C��������ŁA�因����u���̃J���e���[�g�v�̌��~�����o����o���Ă���B
�@���̓N���u�ɓ���Ȃ��j�ŁA�������l�ő�R�̎�Ő����c�����A���J�����ɍ~��Ă���ƁA�[��ɛ����̃J���e���������o�肽���Ƙb���A���T���ɓo�邱�ƂɌ��܂����B
�@���ɂ��ƁA�因����̋����[�g�ɓo�邽�߂̕X�̃����[���S�O���o���ǂ��Q�O���o��ƃe���X�ɏo��B
�@�[��͂��̃e���X����S�O����t�̑�g���o�[�X�����Ƃ��ȒP�ɍς܂����B
�@�g���o�[�X���I���}�s�ȕǂ��S�O���o��B
�@��������n���O��̕ǂ͋ɏo�Ȃ���g���o�[�X�C���ɍ��シ��ƁA�j�S�����̃J���e�̊�ɒ����B
�@�����n�[�P���e���X�Ŋm�ۂ���ƁA�[��̓A�C�X�n�[�P����ł��Ȃ���n���O�C���̕ǂ��A�C�[���̒܈�{��10�p�A20�p�Ƃ��肶��Ɣ����オ��A������˔j���đ因���̓��ɗ������B
�@�[��Ɠ��͑因���̓�����因����̒������U�C���ō~��A�܂��A��g���o�[�X�����ċ���̃��[�g�ɍ������ĕX�̃����[���������B
�@�N�Ɠo���Ă��A�������߂Ȃ������B
�@�ق�̏�����������ł͖����Ă��܂��̂���ł������B
�@�����A�[��͌����ď��̎q��o����o�R�̒��Ԃɂ͓���Ȃ������B
�@�������A����q�˂���ƁA�t�߂܂ł͘J��ɂ��܂��ē��������A��ɓo��Ȃ������B
�@���̎q���k�Ǒ��ɓ]����������Ƃ��ɂ́A�^����ɋ~���ɏo�����A�~��������͑��̎҂ɔC���Č����Ĉꏏ�ɉ��R���Ȃ������B
�@�����ɂ������s�b�P���͎�ɂ������Ƃ��Ȃ��A�����̈��������g�p���Ȃ������B
�@����N�̂S���A�[��͒P�Ƃŏ����ȃU�b�N��w�����ƁA���������珬���Ȋ�ł�o��A�ۃ��@����U��q�R�̕��ɉ���A�U��q��ɍ~��鑐�t�̎Ζʂ�����n�߂��Ƃ��A���炩�̌����Ŋ�������k�̏�ɏo�Ă����ɓ�����S���Ȃ����B
 |
 |
�@���싞�q�́A�[�얞�̑����V���Œm��ƁA�F�l�̑���h�~������ɓd�b���A�[��̏ڂ��������B
�@����́A�F�l�̍��X��K�˂�ƁA�[��̐���������f���A�R�̏�m�邱�Ƃ��o�����B
�@���X�̘b�̒��ɁA�[��Ɛe���Ȓ���������q���߂̏o���m�邱�Ƃ��ł����B
�@�[��͎R�A�̂��钬�̗T���ȉƒ�Ɉ�����B
�@���a�R�O�N�T���A���ƕꂻ���Ė��͐e�ނ̖@�v�Ŏl���̍����ɍs���A�A��ɍ��S�̉F���A���D�u���_�ہv�ɏ�D�����B��q�͑唼�������w�Z�̏C�w���s���ł������B
�@���_�ۂ͖��̒��œ������S�̉F���A���D�u��O�F���ہv�ƏՓ˂��Ē��v�B
�@���̂ɂ�蕃��Ɩ����S���Ȃ����B
�@�D�̖��O�̗R���͍����s�ɂ���u���_�R�v�A���D��5��̏Փˎ��̂�����A�D�́u���ˊہv�Ɖ��̂��ꂽ���A���a35�N�Ɂu�����h�ہv�ƏՓ˂��u�����h�ہv�����v���Ă���B
�@�e�ނ̏��Ȃ������[��́A��l�Ő����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ�A���Z�����ނ��{�Ђ������ɂ���q�g�s�̏����ȉ�ЂɏA�E�����B
�@�ʋ���r���Ō����R�́A�ʐ^�Ō���A���v�X�̗l�ɑf���炵�������B
�@�~�̒��A�V�_��̒|�c�����猩���R�́A�R���݂����Y�����ŃO���Ɨ����オ�葼�̎R�X�����ɂ��Ă���B�@
�@�[��͒��w�̎��A���Ə��߂ēo������R�ɓo�肽���Ȃ����B
�@�R�̎Q�l������Ă��ēǂ�ł���ƁA���قɔ��܂�Ȃ��œo��ɂ́A���J�����ɂT�O�~�����Ώh�����o���邱�Ƃ�m�����B
�@�[��͂P�P���̏I���ɑ�R���̃o�X��ɍ~�藧���A�o�X��̏�ɂ���Ǘ��������ŁA�o�R�͂ƁA���J�����̏h�������ƁA�W���̓���o���R���̉�����ᓹ�ƂȂ�A��_�R�_�Ђ̊K�i�͐�̎ΖʂƂȂ葫�Ո�c���Ă��Ȃ������B
�@�_�Ђ̋����ŋx��ł���j�Ə�����l�̓o�R�҂��オ���ė����B�j�̕��Ɍ��o�����������B
�u���X����ł͂Ȃ��ł����v
�@���X�́A�[��̍��Z�̐�y�ł������B
�@���X�̏Љ�ŁA���X�̍���ґ���Ɓu��q�v�Ɩ���鏗���ł������B
�@��q�́A�Ďq�̊Ō�w�@�̏�������Ă����Y��Ȑl�������B
�@�S�l�œo���Ă������A�[��͗ւ̒��ɂ͓���Ȃ������B
�@�Ȃɂ������Ɍ��������q�̖ڂ��C�ɂȂ��Ă����B
�@�����̋�����m���Ă���̂ł͂Ƃ������߂������������B
�@�[��̑���́A���~�̎R�ɂ͕n��ł�����Ȃ����̂������B
�@���J�����ɒ����Ɣނ�͓V��̊Ԃɓ��������A�[��͊O�ŐQ��ƌ����ď����̊O�ɏo���B
�@���̂Ȃ�[��͏����ɂ͐Q�����Ǝv���Ă������߁A���܂鑕����������Ȃ��A��Ⴂ�ȏ��ɗ��Ă��܂����Ɗ����Ă����B
 |
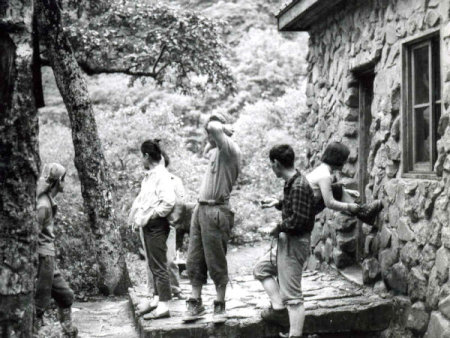 |
�@���X�́A�����̋߂��̃u�i�̍��{�ɂ����[��ɁA�c�G���g�Ƃ����i�C�����̊ȒP�ȃe���g�ƁA�܂����C�̗������Ǝ��������o���Ɓu���߂�ȁv�ƁA�ӂ�Ə����ɏ������B
�@���X�́A�[��̒u���ꂽ�����⌻�݂̏�m���Ă����B
�@���߂Ȃ��������߂�ƁA�[��͉��̂��܂��o�Ă����B
�@�����o�Ă���������߂Ă���ƁA���̖�̔��̂��߃E�g�E�g�ƐQ�����A�����ɖڂ��o�܂��ẮA�܂��A�Q�悤�Ɠw�߂��B
�@�������ɂ́A�V�Ⴊ�~��n�߁A�[��͐k���Ȃ��璩�̗���̂��Ђ�����҂����B
�@���Ƃ����܂Ŋ撣���ď����̒��ɓ���ƁA��q���g���������������o��
�u�������́A����ɍs����ł����A�s����܂����v�@�ƕ����Ă��ꂽ�B
�u�l���A���̗\��ł��v�@�ƁA������̂�����t�������B
�@�R�l�̈�Ԍ�ɑ����čs�Ҕ�����o���Ă���ƁA��q�̕�����u�ǂ���ɂ��߂ł����v�ƕ����Ă����B
�u���̗F�B���A�M���̍H��̊Ō�w�����Ă��܂����A�������ł����B�v
�@�[��̍H��̋~�쎺�ɂ́A�Ō�����Ă��鏗���͈�l�������Ȃ������B���ꂩ��A��l�̘b�́A�f�ГI�ł͂��邪������ꂽ�B
�u���O�݂͂�B���߂Ə�����ł��B�v
�u�l�݂͂�B���ł��B�v�ƁA���߂ē�l�̋��ʓ_�������������Ƃ��o�����B
�@���X�́A�R����~���Ɛ[��̓o�R����Ȃ��Č��Ă����Ȃ��A���������[�_�[������Ă���R�x��̓�������߂��B
�@���X�ɏЉ�ꂽ�X�ŁA�[��͂��̔N�̃{�[�i�X�ŏ��߂Ă̓o�R�p��������A�Q�܂����͍��z�Ŕ����Ȃ��������A�p�c�Ƃ����E��̐�y���ČR���o�̐Q�܂������Ă��ꂽ�B
�@�[��́A�H��̊Ō�w�ɍ�q�̋ߐ���o���ƁA�t�̎R�ɗU�����B
�@�t�̎R�́A���X�̉�͒j���������A�V�l���@�̖ړI�ŕ�W�����B
�@�j�����́u�t�̑D��R�v���������A��q�͗��Ă��ꂽ�B
�@���߂Ɛ[��̎p�́A�y���ɂȂ�Ƌ߂��̎R���o��̃Q�����f�Ɍ���������悤�ɂȂ�A�j�����̉�ɏ������邱�Ƃɂ��đ��̉��������o�Ă������A���X�́A�[��̋�����b������̓��ӂ����t���Ă�����B
�@��R�̊�o���A�k�A���v�X�̍��h�ɓ�l�͎Q�����r���Ă������B
�@�[�삪��t�����ˎs�̍H��ɓ]����ƁA���߂͊Ō�w�@��ސE���āA�����̒ϓ��ɂ���H�J�a�@�̊Ō�w�Ƃ��āA�����ϓ��̗��ɓ������B
�@�T���̒J��x�ɓo�邽�߁A�[��͒ϓ��̗���q�˒J��x���ӂ̎R��o�낤�ƗU�����B
�@��씭�̖�s��ԂŒJ��x�ɏo��������A�O��A��A���v�X�A�씪�c����o��A�䍂�̑O�䓌�ǂ��J�̊e�ǂ�o�����B
�@�[�삪�A�R�A�̕Ďq�H��ɓ]����ƁA���߂͕H�J�a�@��ސE���A�Ďq�ɂ��鑍���a�@�̊Ō�w�Ƃ��ċA���Ă����B
�@��l�͏t�̑�R�ɓo�邽�ߌ��J�����ɓ���ƁA���߂̑��Ƃ������Z�̉��t���싞�q�ɏo������B
�@����͈����R�x��ɏ��������挧�R�x����̗��������߂Ă����B
�@����́A�t�̒n���J�͑�̘A���ŁA�R���L�x�őf���炵���ƁA��l�ɐi�߁A
�u������ł��A�n���J�̋�����ɓ���邵�A���͌��J�����ɂQ�E�R���������ł���B�v
�@�ĉ������B
�@��l�́A���J���璆���z�o�R�Ń��[�g�s�A�ɏオ��A�����Œ��H��H�ׂ�ƐU��q�������n�߂�ƁA��R���L�̖��ɕ�܂ꂽ���A����̃f�u���ɕ���ꂽ��k�ƂȂ�U��q��͕����₷�������B
 |
 |
�@������ɒ������ɂ́A�_�̐�Ԃ��甖�����R��Ă����B
�@4�����߂̋�����͓�����������ɖ��܂�A�����̒��͐^���Â������B
�@�����ɉו�������Ɠ��ǂ̒�@�ɏo�������B
�@�c��̃L������L���������������A�n���J�̏㕔�ŕ����V���R�W�߂�Ə����ɋA�����B
�@��l�����̗[�M�́A�}�}�S�g�̂悤�Ŋy�����A�n�������ł��R�݂̂��`��V�Ղ�A�|�݂��a�����ŁA������y����ł���ƁA�Ďq�̍��Z������R�̓�ǂɂ���A�O�̑�̏������璹�z���o�R�ŏオ���ė����B
�@�����̐搶�́A
�u��������U��q��̏㕔�Ő��P��������v�Ƙb���A�[���
�u�n���J�����x���o�R�ŐU�q�R�A���J�ł��v�Ɛ��������B
�@���̓��ɐ��k�B�ƕʂ�A�[��B�͐搶�ɍ����̒��߂��ɂ́A���[�g�s�A�߂��ʼn��Ƃ����ď������o���B
�@�n���J�̒����͒x�����A���k�B�Ɍ������āA��l�͌��J�̉���搶�ɉ���߂ɑ��߂ɏo�������B
�@�n���J�͐�ɕ��������₷���A�E�݂ɉG�J���痎������A���݂̖��̂Ȃ����A��x�̑ꓙ�̔������������e�z���y���݁A�����ĒJ�����܂����S���W�F�͉E��̐�̎Ζʂ�o��͌��ɍ~�藧�����B
�@�����͐���������W�ߑ����Ȃ��Ă����B
�@�傫�Ȑ𗘗p���Ί݂ɓn���ѐ̎��A�[��͎�������o���A�̏�ňꏏ�ɂȂ����Ƃ��A���߂Ď���q���ł��邱�Ƃɖj����߂��B
�@���������A���ɉ͌���t�ɐ������ꂾ���ƁA�C��E�������œn���������F�ɕς�����Ƃ����ẮA���݂������ߍ������������B
�@��R�ꂩ��}�ȑ�R�Ó�������A��x�̏����ŋx�e����ƁA��c���R��ڎw���o��n�߂��Ƃ��A���߂��s�b�P����������ɖY��ė������Ƃ��v���o�����B
�@�[��́A���k���U��q��Ő��P�������邩��A�����Ă��Ă���Ă�̂ł͂ƁA���߂ɘb�����B
�@��c���R�̉����e�w�s�[�N�̓o�艺��͖ɒ͂܂�Ȃ���z�����B
�@�U��q��̌����鏊�܂ŗ��Ă݂�ƁA���P���P���̕��i�������A�[�삪�u���[���v�ƁA�Ăт�����ƁA���k�̈�l���s�b�P����U���Ă����B
�@���߂̓s�b�P�������ɍ~���r���ŁA�[���
�u�U��q��̏㕔�̔����́A�O�䍂�̖k�����ɂ�������l�B�v�@�ƁA�U��������B
�@���̎��A���߂̐g�̂��s���R�ɗh���ƁA�U��q��Ɍ������Ċ������Ă������B
�@�[��́A�����o���Ȃ������B���߂̐g�͓̂�x�O�x�o�E���h����ƁA��̎Ζʂ��Q�O�O�����������B
�@�[��́A��̎Ζʂ܂ʼn���ƃO���Z�[�h�ʼn���A���߂�����N�����A���O���Ă��Ԏ��͋A���Ă��Ȃ��B
�@���������Y��Ȋ�����Ă��āA�܂�Ő����Ă���݂����������B
�@���]�����ނ͉����o���Ȃ������B
�@�Ďq�̐��k�B�������Ă���ƁA�����҂Ɉ�t�����āA�S���}�b�T�[�W���{�������A���炭���Ĕ��߂̎��S��鍐�����B
�@���߂͋}�Ȋ����ɂ��S������ɂ��ˑR���ł������B
�@���̌���ɋ}�s�����R���̒��݂��A���J�����ɂ���X�m�[�{�[�g���g�s���悤�Ƃ����Ƃ��A����͐U��q��̎��̂�m�����B
�@�[��͉�Ђ����߁A���S�����悤�ɎR������A�e���g��Q�܂������Ȃ��ŁA�R�̒��ɐQ���肵�Ă͑�R���̒���f�r���Ă����B
�@���X�͐[��̎p�����߂đ�R���ӂ�T���A���R�L�����v��Ǘ����x�����_���ŐQ�Ă���[��������o�����B
�@���X�͐[��ƎR��������ɐ��������āA�ނ̐S���Ƃ������A��R�[�ɂ��鍁��J�̐��{�Ă��Љ���B
�@���{�͍��X�̌Â��R�̗F�B�Ő[��Ɣ��߂̎��͒m���Ă����B
�@���{�̖q��ł́A�ނ͈�S�ɓ���������Y��悤�Ɗ��𗬂��A��͒��̘J���̔��Őg���났�����Ȃ��Ŗ��肱�����B
�@�H�ɂȂ�A�q���̊��荞�݂⊣���̎d�����Ȃ��Ȃ��Ă���ƁA�q�ꂩ�猩����O�ؕ�̃s���~�b�h�ȉs��̗Ő��߂鎞�Ԃ������Ȃ��Ă����B
�@���{�́A�~�̊��Ԃ�������悤�X�L�[��̎d����i�߂����A�[��͑�R�̗Ő��ɐV�Ⴊ����ƁA�t�܂ő�R�ɓ��肽���Ə������n�߂��B
�@�V�Ⴊ�~��q���̎d�����I���ƁA���悩���l�����āA���J�ɓ���[��̎p�����N������悤�ɂȂ����B
�@�����ŏ��߂ĉ�l�ɂ́A�����̂��Ƃ��u�[����߁v�Ƙb���A�������l�́u���߁v�ƁA�s�v�c���������B���̗��R��ނ͒N�ɂ��b���Ȃ������B
�@�[��́A���N�S���ɂȂ�q���̑����L�юn�߂�ƁA���̓~�̍Ō�Ƃ��āA���J��������U��q���ʂ��ċ�����ɓ���n���J������A��x�����獁��̖q��ɋA���Ă����̂���ł������B
�@����N�̏t�̑�R�́A�[��ɂƂ��čŌ�̎R�o��ɂȂ����B
�@���̎����A���߂̃s�b�P���͓V��̊Ԃɂ���A�I�̏�ɂ͐Q�܂��������B
�@���싞�q�́A�[��̎��̈ȗ���R��n����ɓ���̂�����Ă����B
�u�������n���J��i�߂Ȃ���E�E�E��l�̐U��q��̌������E�E�E�v�ƁA�����閈���������B
�@�������A�R�A�̎R���Ԃ��v���ɑ�R�ɏW�܂�u�R���y���މ�v���Â��ƕ����āA���N�Ԃ�ɑ�R�ɏオ���Ă����B
�@�Q�܂̂���ꂪ����ƁA�����̘A���͐[��̕ČR���o�̐Q�܂���������ʼn����A�I�̏�ɕԂ����B
�@���̖�́A�\�O��̌��Ŗk�ǂ͗H���̐��E�ɕ�܂�A�߂����������p�����Ă����B
�@�S���̎R�ɂ��Ă͗₦���݁A�����̒��͒��Ԃ̓f�����ŕǂ͕X���A�L���L�������Ă����B
�@�F�̐Q�����n�܂�A�����̒��Ɍ��̌�����������ł����B
�@�ӂƁA����͖ڂ��o�ߕǂ�����ƁA���̌���������Ȃ��ǂɐ[��̏㔼�g�������сA���S�o���h�𒅂��ĉ���̕������߂Ă����B
�@���삪�����o�����Ƃ����Ƃ��A���ԒB�݂͂�Ȃ��N�������Č݂��Ɋ�����n�����B
�@�Q��O�ɁA�Q�܂��������҂͑S���[������Ă����B
�@���̖邪�A�[��������Ō�̖�ł������B
�@�u�R���y���މ�v�Q���ҒB�͗����S���ŁA�����Ɏc���Ă����[��̐Q�܂�H�퓙�������āA���J�������o�����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɔ��߂̃s�b�P���͌����Ȃ������B
�@�U��q���ʂ��ċ�����ɓ���A�L������̌����鋛�f�m��̉��ɐQ�܂�H�퓙�߁A�ΎR��z���A������킹�悤�Ƃ����Ƃ��A��̏�Ɉ�{�̃s�b�P�����������B
�@�������o�鎞�ɂ͌�����Ȃ��������߂̃s�b�P�����B�s�v�c�Ȃ��Ƃ����A�^���͂킩��Ȃ������B
�@���߂̃s�b�P���͎R�ɓ��肽�����Ă������A�[��͂��̃s�b�P�������߂��E�����Ǝv���A�����܂ł������Ƃ��o���Ȃ������B
�@�[��Ƃ��Ă̓s�b�P�����̂Ă邱�Ƃ��o�����A�N�����R�ɘA��čs���Ă���邱�Ƃ��A����Ă����̂ł͂Ȃ����B
�@�������āA�[��̃P�����ɓY���āA����Ɠ�l�͈ꏏ�ɂȂ����B
�@�[��̃P�����Ƃ��Č��Ă����A�N����ƂȂ��u�݂�P�����v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B
�@�����A�����ɂȂ�A���́u�݂�P�����v�͒N�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���ǂ̊����̂��ߖ��܂�A�n�`���ς�����B�����A�t�߂ɂ́A�c��̍��ɂȂ�Ɓu�����V�v����R�o�āA���̋߂��ɂ݂�B������̂��Ǝv���o���Ƃ����B
�@���ꂩ��\���N���������J�����̃U�C���Ղ�ɁA���X�Ɖ���͏o������B���X��
�u���߂̃s�b�P�����A�Ȃ�Łc�v
�@����͐Â��Ɍ��n�߂�
�u�����A���{����ɗ���ł��B�s�b�P�����c�v
���Ƃ���
�@����́A1970�N��̌��J�����ɓ`������b�����ɁA�n�삵�����̂ŁA�����L�����Q�܂͓�����w���̕��ŗH��Ƃ͊֘A������܂���B
�@�����J�����ɁA�N�̕�������c����Ă��ėH��͖{���ɏo�������ł��B
�@�V��̊Ԃɂ͏㔼�g�̗H�삪�A�O�̊Ԃɂ͕�����`���H�삪�c�B
�@��R�͐��̒J��x�Ƃ����قǁA����̔�������댯�ȎR�ł���B

|