ベン・シャーン
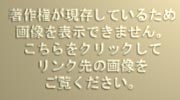 |
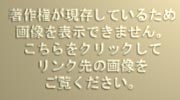 |
ベン・シャーンの描く無表情は、乾いたものであっても、決して虚ろなのではありません。
一度はパリでフランス近代絵画を学び、風景画などをものしていた画家が、なぜサッコ・ヴァゼンティ事件やドレフュス事件等を題材として、絵筆によって現代社会を切っていったのか。
「人種の坩堝」と呼ばれるアメリカ。しかし実際には「坩堝」中の形質は、多くの場合混じり合おうとはしないのかもしれません。
様々な形で起こる差別。疎外感、絶望感。それらをベン・シャーンは他人事としてではなく、自分自身・・・・・・ニューヨーク大学、ニューヨーク市立大学、ナショナル・アカデミー・オブ・デザイン及びアート・スチューデンツ・リーグ等と名門に学びながらも・・・・・・受け止めながら過ごした人間でした。彼はリトアニアからの移民であり、ユダヤ人であったからです。
街に存在する孤独感を誰よりも知りながら、退くことをしないベン・シャーンの、揺るぎないリアリズムに満ちた冷徹な視線は、一種清冽な迫力を持って、異邦の民が生きていくとはどういうことかを訴えかけているような気がします。*サッコ・ヴァゼンティ事件(1931−32年 二人のイタリア系移民が強盗殺人の容疑者として処刑されたが、かれらがアナーキストで、徴兵忌避者であったが故に、との疑いがあって、改めて調査委員たちによって真相を「解明する」という形になった)
*ドレフュス事件(売国疑獄事件としてフランスの国論を分けた事件。1894年ユダヤ系の参謀本部付砲兵大尉アルフレッド=ドレフュスが陸軍の機密書類をドイツへ売却したとの疑いで、終身刑に処せられた。これに対して98年以来作家ゾラに代表される知識人が当局を弾劾、軍部や右翼がこれに反論。のち真犯人が明らかになってドレフュスは99年釈放、1906年無罪)