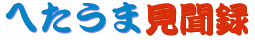大部分の方は「誰、その人」と言われると思います。文楽人形師というのは、文楽つまり人形浄瑠璃で遣う人形の首(かしら)を作る人の事です。文楽人形は役の性質によって遣う首の種類が決まっています。演目が決まると、首に化粧をほどこし、カツラをつけて、その役らしくととのえます。現在、大阪の国立文楽劇場で遣っている首の大半は大江さんの作品だそうです。
文楽人形は左手の指の操作ひとつで目や眉や口が動きます。うなずいたり笑ったりもします。首の中に仕掛けがあるのでそう動くのです。作成には、高度の技術が必要です。
大江さんの作った人形には品がありました。昨年観た「菅原伝授手習鑑」の千代。わが子を失った千代が、白装束で踊ります。その美しかったこと、品のあったこと。ほうかむりからチラと見える千代の顔にうっとりと見惚れてしまいました。
昨年、「大江さんを人間国宝にしよう」という署名のチラシをいただきました。どうして、伝統芸能を支えている大江さんの様な人が、人間国宝にならないのだろうか? もっともだと思います。いい人形がなければ、いい人形遣いの芸の魅力も半減してしまうでしょう。舞台は総合芸術です。たくさんの職人さん・裏方さんの力があってこそ成立しているのです。
そういった点で、伝統芸能の未来は暗いと言えるでしょう。大江さんの様な職人さんが減ってきているのです。彼らの技術、そして経験が、次世代に伝わっていく前に消えていってはどうしようもありません。また、材料の問題もあります。生活や環境の変化で、伝統芸能に必要な材料が失われたり、質の変化(悪化)が起こっています。一度失われた伝統を取り戻すのには大変な努力と時間がかかります。それは、私達自身に精神的に影響を与えていくのではないでしょうか?
最近、昭和50年代の歌舞伎のビデオを観ました。役者さんの芸も素晴らしかったのですが、何よりびっくりしたのは「つけうち」の音。殺陣などで「パシッパシッ」と威勢のいい音のするアレです。あのビデオの中の音は素晴らしかった。あんないい音は、現在の歌舞伎では多分もう聞かれないと思います。
失われたものは、確かに、大きいのです。
(96/01/31)
 オレンジリンク「伝統芸能」へ
オレンジリンク「伝統芸能」へ(伝統芸能関係のWWWを紹介しています)
|HOME|What's New|Mail to Me|Help Map|