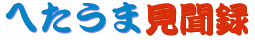
|
日曜日の朝、プレイガイドのおじさんは店を開けるなりこう言った。「キヨシロ?」。 正確には、「忌野清志郎/ラフィータフィー マジカデ・ミル・スター・ツアー」のチケットのことだ。会場は小さなライブハウス。まさに「間近で見るスターツアー」。 忌野清志郎は、気になる存在だった。どちらかというと、彼の歌よりも、過激な行動やテレビのトークが気になっていた。彼の行動やトークには芯があり真面目だ。 このツアーも、長年の清志郎の大ファンという友人が「行きたい」と言わなかったら、きっと行かなかっただろう。 ライブ直前には、清志郎のドキュメンタリー映画「不確かなメロディー」が公開された。ライブと上映期間が重なっていたので、「舞台あいさつがあったりして」と言っていたら、本当に舞台あいさつがあるというではないか。 舞台あいさつ当日、炎天下の中2時間並んだ甲斐あって、3列目をGET。立ち見も出た満員の観客の歓声の中、忌野清志郎とラフィータフィーのメンバーが入ってくる。せいぜい70人しか入れない小さな映画館は狂喜乱舞。 清志郎は「今日、姫路から岡山まで自転車で走ってやってきました。99.2キロ。ホテルのまわりを一周して100キロにしました!」、と元気に報告。真っ赤に日焼けした腕を見せながら自転車談義を始めるのだった。清志郎は自転車にはまっている。ラフィータフィーのメンバーも含めて、全員がツアーの合間に自転車で走っている。タフな人たちだ。東京から鹿児島までツーリングを行う予定なので、その下見も兼ねているらしい。しかし、国道2号線を自転車で走るのはいいけど、バイパスは危ないから走らないように。 その後に上映された、「不確かなメロディー」は、よくできたドキュメンタリー映画だった。自身の音楽生活30周年記念の武道館コンサートを成功させた直後に行われた、日本全国のライブハウスを巡るツアー。清志郎にとって、音楽生活の原点を見つめ直すツアー。映画は、ライブやその土地の風景に、清志郎やラフィータフィーのメンバーの日常生活やインタビューを織り交ぜながら、「忌野清志郎」というアーティストの生き様や信念を伝えている。 忌野清志郎は、ステージではとても派手なのに、実際はとてもシャイだ、とメンバーはいう。インタビューを受ける清志郎は、淡々と静かに語っている。その言葉のひとつひとつは重い。まだ若く有名でなかった頃、レコード会社との契約で、レコードが出せない時期もあった。才能があっても認められない苦しい日々。彼は、アコースティックギターをエレキギターに変えることで、新しい表現方法を見つけ、成功していく。 表現方法が変わっても、成功しても、忌野清志郎は変わっていないんじゃないか、と私は思う。彼のやっていることは芯がある。彼が時代に寄ったのではなく、時代が彼に寄ってきたのだ。「夢を持ってるかい!? 俺には夢がある」と叫ぶ清志郎は、とてもまぶしくうらやましい。 翌日、舞台挨拶と映画の興奮がさめやらぬまま、ライブに突入。小さなライブハウスに、こんなに人が入るのか!?と思うくらいに人がいる。開始時刻より10分ほど遅れてライブスタート。人の山が前に横に移動する。そのすぐむこうに、忌野清志郎とラフィータフィーのメンバーがいる! 始めてライブで聞く忌野清志郎の歌に、びっくりした。彼の歌は、皮膚にしみいってくる。歌の意味がよく分かるのだ。これだけ「心」を伝えてくる歌い手とは知らなかった。 何千人もの観客を相手にできるパフォーマー忌野清志郎は、同じエネルギーをわずか150人の観客に向けて放出する。観客は興奮状態になった。気がつけば、身動きも取れない狭い会場で、腕をふりあげ、叫びながら一緒に歌っていた。幸せだった。 ド派手なパフォーマーは、客席に近づきTシャツをたくりあげ、胸のペイント刺青を見せながら、頭の後ろにギターをまわして弾いている。何人もの女たちが腕をのばし、胸の刺青を腹をまさぐる。後ろに身を引いた清志郎は、ほんの一瞬はにかんだ表情を見せた。きっと、彼の素顔に近い表情。「彼はシャイだ」。映画の中のメンバーの言葉がよみがえった。 武田真治のサックスは照明にきらめきながら弧を描き、藤井裕のギターはいぶし銀の味わいを出し、宮川剛のドラムは炸裂しまくって、ごきげんなライブも終わりに近づいた。ラストナンバーは「君が代」。髪の毛にムースをつけ、スプレーしまくるド派手なパフォーマンス。「よい子はまねしてはいけません」。清志郎が投げた櫛が、私のところに飛んできた。かがんで取ろうとしたのに暗くて見つからず、隣の人が取っていった。 すべての音楽が終わり、すし詰め・サウナ風呂・酸素欠乏状態で熱狂していた観客も、静寂と強烈な耳鳴りの中でけだるさを覚え、ドリンクを買い求め喉の乾きを癒していった。しかしすぐに体勢を立て直し、握手会に備える。そう、会場でCDを購入すると忌野清志郎との握手券がもらえたのである。にわかファンの私は、「何を話そうかしら」と一生懸命に考えたのに、実際に話したのは「良かったです。映画も見ました。感動しました」という情けないものだった。清志郎は「ありがとう!」といってくれ、自分からは握手の手を離さなかった。やさしい人だ。舞台で見るとあれだけ大きかったのに、舞台を離れると意外と小柄な人だった。本当のスターは、舞台で大きく見せている。 忌野清志郎をめぐる怒涛の2日間は、こうしてあっという間に終わった。偶然にライブ情報を知り、偶然に映画情報を知り、偶然に舞台挨拶のことを知った。本当に幸運だったと思う。「時代」が寝ている「男」と、こんなに身近に出会えることは、そうないだろう。 だから、とても楽しくて幸せだった。 だから、とても切なくて哀しい。 (2001/8作成 2002/7/21加筆) (C) HETAUMA HONPO 2002
|HOME|What's New|Mail to Me|Help Map| |