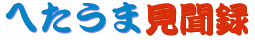「今度、ジミー・スコットのドキュメンタリー番組をNHK総合で再放送するよ」。
知人のH氏が教えてくれた。H氏は、アメリカのジャズシンガー、ジミー・スコットの岡山公演の企画に携わっていた。 勧められるままに番組を観た。ジミー・スコットの声は、今までに聞いたことのないものだった。彼の声は、遺伝的な病気のために、声変わりすることがなかった。少年でもなく女性でもない、神が与えたとしか思えない美しい声だった。
番組はジミーの人生を、彼や家族、ファンたちへのインタビューを交えながら静かに伝えていた。 1925年7月17日生まれ。本名ジェームス・ビクター・スコット。早くに家族の中心だった母親を事故で亡くし、残された10人の兄弟は全員施設で育てられた。10代の後半に、たまたま歌ったのが認められ、1948年からライオネル・ハンプトン楽団のボーカルとして活躍する。当時の芸名は、「リトル・ジミー・スコット」。病気のために彼の身長は150cmに満たなかったのだ。やがてソロとして活動したが、レコード会社のギャラは不当に安く、まるで奴隷のような扱いだった。ジミーの最高傑作といわれるアルバム”Falling Love is Wonderful"は、契約トラブルから発売中止にされた。別のアルバムでは、ジャケットカバーを勝手に女性モデルの写真にされ、彼の女性的な声を利用したとしか思えない行為を受けた。ジミー自身も、幾度もの結婚・離婚、アルコールに苦しんでいた。やがてジミーは故郷に戻り、その後20年近くショービジネスの表舞台から消えてしまう。
ジミーの歌をこのまま埋もれさせまいと活動していた音楽プロデューサー、ドグ・ポマスの死がジミーの運命を変えた。ドグ・ポマスの葬儀でジミーが歌った"Someone to Watch over Me"。辛く哀しい人生を経た天使の声が奏でる鎮魂の歌。これを聞いたレコード会社の社長がジミーに契約を申し出て、彼はショービジネスの世界に復帰したのだ。
完成度の高い素晴らしいドキュメンタリーだった。感動した私は、早速に岡山公演の一日二回通しチケットを買い求めた。 当日の会場は、「デスペラード」。席数150の小さなライブハウスだ。開場2時間前から並び最前列の席を確保した。
最初にピアノトリオのインストルメンタルが続き、期待が高まる中、ジミーが黒のスーツと蝶ネクタイ姿でゆっくりと登場した。やっと、あの声を聞くことができた。女性とも男性ともつかない不思議な声。とても74歳とは思えない、声の艶とボリューム。まるで仏様のような、慈愛あふれる穏やかな笑顔が印象的だった。
この夜のライブは「ミラクルナイト」と呼べる程、特別なものではなかったか? 2回目のライブで、ジミーを始めメンバーのテンションがグッと上がり、満員の観客を巻き込んで素晴らしい歌と演奏を繰り広げ、感動を共有していった。
"Sometime I Feel Like a Motherless Child"には、母親を早くに亡くしたジミーの人生が投影されている。バンドメンバーが、ジミーの醸し出す悲しみの中に、ゆらめきながら演奏していた。
"Sorry Seems to be the Hardest Word"。このピアノだけをバックにした曲は、まさに哀しみの極みだ。ジミーは、全身から感情をほとぼらせながら歌い、聞く者の心に触れていくが、触れられる瞬間に辛い痛みを伴う。それは、ジミーの心の痛みであり、聞く者自身の心の痛みでもあるのだろう。
最後は、明るいテンポのある曲で観客と一体になって盛りあがった。小さな会場が熱気に包まれ、観客はスタンディングオベーションでジミーとバンドメンバーに感謝した。
メンバーと肩を組みながらあいさつするジミー。あまりに舞台と観客席が近いので、何度もあいさつをしていく内に、みんな照れていた。このライブの中で、ジミーと私たちの間に心の交流があった、と思っている。私は、「どんな事があろうと、この世は美しい」と、ジミーが歌うのを聞いて何度も思った。 ジミー・スコットのCDは、日本でも数枚が発売されている。私のお勧めは、20数年前に発売中止となった"The Source"(ジミーには、発売中止となったアルバムが2枚ある)をメインにして復刻した"Lost and Found"と、最近のロックやポップスのヒット曲をカバーした"Holding Back the Years"だ。特に後者は、ジミーの自然な歌い方が心地よく、深い味わいのある名盤といえよう。この6月に最新アルバム"Mood Indigo”も発売された。こちらは、モダンで抽象的な仕上がりになっている。
しかし、ジミーの本当の素晴らしさは、録音に入りきらないところにある。今年の11月に再来日するという、うれしいニュースを聞いている。
ジミー・スコットの歌を、心の耳を傾けて感じて欲しい。きっと、何かが見つかるだろう。 (2000/7/22)
(C) HETAUMA HONPO 2000
|HOME|What's New|Mail to Me|Help Map|